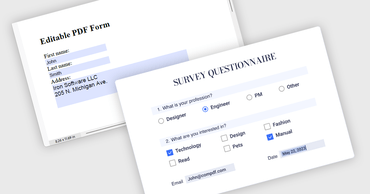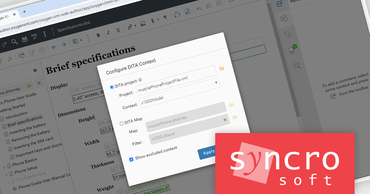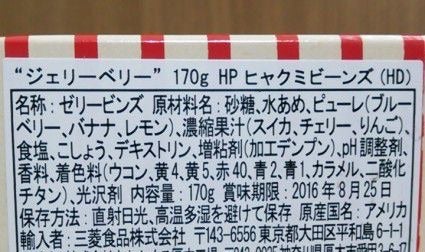「頭の中にある意識ばかりを大事にし、心の感覚を大事にしていない…そんな時代になったのは、なんでもかんでもすぐに答えを求めようとの姿勢から起こった。知識ばかりを詰め込んだ今の頭でっかちな若い人をみていると、もっともっと自由に生きられるのではないか」。と、これは話題の著書『遺言』の中で養老孟司氏が述べている。考えない若者もいるにはいるが。
が、総体的にみればつまらない若者が増えたのかも知れない。若者はこども時代に得るべきものを得ず、つまり、こどもの純粋な感性を育むことなく、大人の書いた図面を拠り所にしてきたのではないか?こども時代の記憶は何より遊び。お兄ちゃんたちから伝えられてきた、「かくれんぼ」や「缶蹴り」などの伝承遊びを楽しく引き継いできた。それらがある世代で止まった。
さまざまな、「伝承遊び」の中で、鬼が出てくる三つの遊びについて考えてみる。「鬼さんこちら、手のなるほうへ…」、これは幼児を目隠しにして大人たちが手をたたいて引き寄せる遊びだ。おそらくこれは耳という感覚器官に意識を集中させると同時に、目の見えない不安から目の前の障害物を怖れるあまり、鬼の手は宙をまさぐる。これは触覚を重視する意識であろう。
単純だが学習効果を織り込んでいる。それが遊びである。こどもの「遊び」についての心理的特性を端的にいえば、「遊び・遊ぶことは何より快楽」である。したがって、本質的な満足をもたらすものでなければならない。傍目には辛く苦痛を伴っているように見えても本人は楽しみである。例えば、馬跳びとか、おしくらまんじゅうとか、現代では危険とされる遊びもある。
馬跳びの記憶をいえば、受け方として小学年の低学年の我々が、相手の股の間に頭を突っ込んで踏ん張る。そこに大きな中学生の兄ちゃんがつぶすために勢いよく背中に乗ってくる。それは乗ってくるなんてやさしいものじゃなく、ドーンと押さえつけてつぶそうとする。下の子はつぶれないよう必死で頑張るのは、つぶれることで迷惑がかかるからである。それはもう涙目の様相。
遊びによって頑張ること、耐えることを身につけるのだが、必然的に精神力も足腰も鍛えられることにもなる。これを児童心理学的にいえば、自己意識の発達ということになる。つまり、遊びは不快を快に変えてしまう要素をふんだんに持っている。こんな素晴らしい伝承遊びをしなくなった子どもたちを、正直可哀そうに思う。もう少し視野を広げて思考・整理してみる。
「伝承遊び」はなぜ消滅したのだろう。さまざまな原因が考えられる。①地域にこどもの集団がなくなった。②こどもの自由時間が少なくなった。③遊び場の減少。④遊びの高級志向。これらについては、①少子化、②学習塾・習い事、③要所に公園はあるが、宅地開発で空き地の減少は自明。④誰もが貧乏だった時代であり、遊びにお金をかけるほど余裕がない。
この中でもっともこどもをリスペクトしたいのが④である。家が貧乏だからお金のかからない遊びを考えたこどもたちである。そんな時代は大飢饉、大凶作、大恐慌でもない限り二度と復活はみないだろう。メーカーはせっせと高級な遊び機器や機具の開発に余念がない。そんな時代が良かったというのではなく、人はその時代にしか生きられないものだ。
こどもが時代を担うのではなく、時代がこどもを作っている。したがって、遊びの変容は時代の流れであり、遊びそのものの質や遊びの方法の変化は、善悪の問題ではない。上記した「鬼」が登場する三つの伝承遊びとは、「鬼ごっこ」、「かくれんぼ」、「かごめかごめ」が浮かぶ。「鬼」とは、「鬼定め」で、これはこどもの優位関係もしくは公平に順番で決める。
思うに、いつも鬼を割り当てられる子はいた。なぜかといえば、広義でのいじめに似たものだが、陰湿ではなくとも、当人には不満であったろう。彼は否応なしに他の仲間から隔てられ、疎外されねばならなかった。鬼ごっこで鬼を命じられても、足が遅かったりで捕まえることができず、しないには泣いて帰る子もいた。それでも次の日には広場に集まってくるのだ。
泣いた下級生を上級生はいたわり、「今度は俺が鬼をやるからちゃんと逃げろ」。にもかかわらずその子はいの一番に捕まってしまう。これは年齢差、脚力の問題だから当然の結果であるが、それでも一緒に遊んでもらえるという至福感は満たされる。対等・平等が実は対等でなく不平等であって、それは仕方のないこと。そうした理不尽さを超えてこどもは学んでいく。
思想史家の藤田省三は、著書『精神史的考察』のなかで、「かくれんぼ」の鬼体験を以下のように指摘する。「鬼と定められた者の味わう、突然に遺棄された孤独、砂漠の中を一人彷徨する体験というのは、「はずされ者」としての行動を強いられる。鬼は、おいかけ、探し、捕らえることで、懸命に仲間への復帰を目指すのである。それは要請ともいえる行為だ。
もし、鬼がその役割を放棄し、探さない、追いかけないという勝手な動きをするなら、遊びは直ちに崩壊する」。とにかく、互いは互いの役割を精一杯に演じることが必要で、どこを探しても見つからない時の寂寥感、不安感を耐え忍び、それでも見つけたとき、捕まえたときの喜び・至福感。そうした真剣さや一切合切こそ遊びの本質であり、こどもにとって遊びがいかに重要かである。
そんな遊びの中で、「鬼ごっこ」や、「かくれんぼ」でふと思い出すのが、歴然としたこどもの個性である。普通は嫌な鬼役であるが、鬼役を喜ぶ者もいた。彼は足も速く、洞察力に長けていたのだろうが、それがまた鬼を率先してやることで、能力に磨きをかけたようだ。ただ逃げ回る者たちより、一人一人見つけ出す、あるいは捕まえることの達成感を喜びにしていたのだろう。
想像するに、こういう人間が戦国時代や三国時代に勇猛な将軍となる資質だったかも知れない。創造力を膨らませると、たかが、「かくれんぼ」、たかが、「鬼ごっこ」ですら壮大なものになっていく。また、「かくれんぼ」には面白いルールがあって、見つけた相手は鬼側のメンバーとして働く任務を与えられるのだ。これは相互反転性で、鬼を好むものはこれもあったかも。
別の見方をするなら、鬼役の救済措置といえなくもない。将棋でいうところの相手の取った駒を捕虜とするだけでなく、飛車は飛車、金は金としての位のままで自軍の一員として働かせるわけだ。これは陣地の拡大を目指す囲碁とは違って、捕虜に謀反を起こさせる点において人間味が溢れている。誰もこれを非人道的とは言わない。この将棋独特のルールに関する逸話がある。
昭和22年の夏、升田幸三八段は突如日比谷のGHQに呼び出され、米軍係官に将棋に関する事情聴取を受けた。当時は将棋大成会(のちの日本将棋連盟)は任意団体で、法人化申請中だったが、決定権を握るのがGHQであった。そこでこのように詰問を受ける。「チェスとちがって日本の将棋は、取った駒を自軍の兵として利用するが、これは捕虜虐待の国際法違反ではないのか?」
日本にチェスを普及させる意図なのか、戦勝国の傲慢な難癖に対して升田はこう返す。「冗談をいわれては困る。取った駒を使わぬチェスこそ捕虜の虐殺ではないか。日本の将棋は敵の将兵を殺さぬばかりか、そのままの役職でそれぞれに働き場を与える正しい思想である」。「アメリカは民主主義を振り回すが、チェスでは王が危なくなると女(クイーン)まで盾に逃げ回る。
これはいかがなものか」。などと升田は、通訳が困るほどに果敢に出まかせを述べた。これに感心したホイットニー准将は、「君は実によく喋る珍しい日本人だ」といい、土産にウィスキーを手渡したという。戦勝国米軍に物怖じせず、忌憚のない発言をしたのは、升田幸三と白洲次郎であろうか。白洲は最もカッコイイ日本男児といわれ、升田は将棋界に理論革命を起こした。