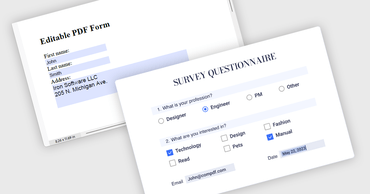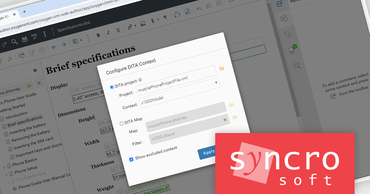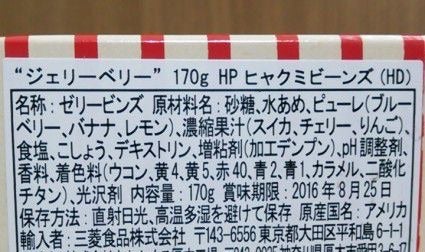親子のこと、夫婦のこと、嫁姑のこと、いずれも家族を中心とした人間関係の問題である。人間が社会的な動物である以上、社会生活の中で様々な人間関係が派生するが、こうしたさまざまな人間関係を社会生活のなかで一生かけて学んでいく。そうしたなか、もっとも身近な家族や家庭を通じて、社会における人間関係の基本的を身につけていくのが手っ取り早い。
両親と子どもからなる単位が家族の原型として、さまざまな社会のなか、こんにちまで変わることなく存続してきたのは意味のあることだ。子どもは成長し、やがて結婚という形で新しい家族を作る。したがって結婚は家族のはじまりといえる。結婚すれば子どもが授かり、子どもが増えればキョウダイという関係も生まれるが、「キョウダイは他人のはじまり」といわれる。
それほどに兄弟姉妹関係は弱いということになる。家制度にあって女はいったん嫁げば、「他家の者」との考えが強く、長男に限らずとも家を継ぐ者以外の兄弟姉妹は、いずれ他家の者になるという気持ちが家族内に強くあった。そのことが、兄弟姉妹関係を弱くさせたといえる。家を継ぐ者と継がぬ者との兄弟間差別は、昔において、それは強いものがあった。
改めて述べるまでもなく結婚は夫婦という新しい単位の設定であるが、それぞれの親との関係が断ち切れるわけではないし、当然にして配偶者の親との関係が生じることになる。一組の夫婦は二組の親との関係に立つことになるが、この関係は夫婦の居住条件よってさまざまな様相を呈する。何より問題になるのは、夫婦優先か親子優先かということではないか。
例えば、小家族形態を理想とするアメリカでは、夫婦は家族の中でいかなる関係にも優先するという信条にたっている。したがって、夫婦のそれぞれの親との関係は、夫婦関係とは同列に論じられないばかりか、拮抗することのない関係となる。ところが日本人は、個々の状況に応じた行為の基準を柔軟に設定している限りにおいて、状況主義者といっていいだろう。
日本人は夫婦関係・親子関係、どちらを優先させるかといった信条はなく、「行為を通じてそのつど自己やシステム(秩序)を生み出す」。つまり、日本人的な自己は西洋的アイデンティティという自己決定的な自己ではなく、ベネディクトがいう、共同社会の外圧に従ってつど決定される自己でもなく、環境変化に応じて自己を限定する自己の在り方のようだ。
そうした自己の在り方が、「人さまに迷惑をかけてはいけません」、「誰とも仲良くやれるよう」という、子どもに対する躾にもなってくるのだろう。燃える火にはそのように向き合い、静かな清流に応じてはそれに向き合うというような自己である。西洋のような、相手が火であろうと水であろうと決して変わらぬ自己同一的(アイデンティティ)な自己ではないようだ。
「行為の絶対基準がない日本人」と、ベネディクトは述べている。行為の善し悪しが内面の心に宿る罪の自覚によって決まる、「罪の文化」に対し、「恥の文化」といわれる日本人の善悪とは、その行為が外側の世間から是認されたり、制裁を受けたりによって決まるようだ。「そんなことをしたら世間の笑い者になる」という状況的外圧に基づいて善行が導かれるという理解でいい。
嫁姑のこと、親孝行のこと、親不幸などについて書いたが、親不幸についてさらに書き加える。響きの良くない言葉であるが、親不幸は必然的な成立過程を辿るものだ。日本人の家制度の考え方は、親が決して、「絶対悪」にならないという前提にあった。たとえ悪い親であるのを知っても、親を、「絶対悪」の立場で論断する心情は日本人に希薄であり、それが文化でもあった。
もし、自分が自分自身を突き放すことができるなら、それこそが自身への思いやりであろう。「察し」という言葉でもいい。ところが日本人はそれができない。自分自身を直接的に絶対者と結合させる信念も宗教もないからである。たとえばある歴史段階において、あるいは社会条件において、そういうものが人々を吸い付け、力を持つことがあったのは間違いない。
しばらくの時の経過が、やがてはそれを相対化の世界へと雲散霧消させてしまう。かつて日本に、日本人に流入した一枚岩的な、単眼的な思想や宗教の辿った運命はそのようなものだった。バカな人間が教祖となりバカな行為をしたことで、そういう奴を神輿と担いだ者がバカでなかったと、どうしていえよう。かつてオウム真理教の幹部だった上祐史浩は当時をこのように述べた。
「麻原を担がなければいけないような周囲の空気観に逆らえなかった」。彼が、「ああいえばジョーユー」といわれたヘタレ理屈こきであるのは、この言葉に現れている。麻原を親とするなら、親不幸ができなかったことへの詭弁である。親不幸をすべきなのにそれもせず、詭弁を弄して立ち振る舞う人間を自分は信用しない。悪には悪として構え、対峙すべきである。
何を言ったところで我が身可愛さの保身である。権威主義が何かも分からず、権威に寄り掛かろうとする宗教など屁のツッパリにもならない。封建社会や封建性が何かも分からず威張る人間も多いが、「思いやり」や、「察し」の心情を我がものとするに必要なのは修練なのか?それでは時間も必要なので、素直で正直な視点で物を観、人に接すればいい。自分はこちらを選びたい。
現代社会の親子や嫁姑に見られる強い反発と隔離は、「察し」と、「思いやり」の無さに要因があると思う。教員と生徒、師と弟子、上司と部下、先輩後輩、そしてチームの監督・コーチと選手、という社会関係においても同じ傾向がみられる。日本人社会の上下関係は封建的で当然という慣例にメス入れてこなかったばかりか、「体育系」という言葉で濁して済ませる。
こういう事象を、「日本人の人間喪失」と自分はみていたが、許されざる者に断固反抗という態度をとってきた自分の矜持である。女子レスリングや日大アメフット部の監督・コーチの在り方が問題になったが、たまたま大きくクローズアップされただけで、こんなことは日常的に起こっていた。すべては人倫的関係の無さを、「体育系」でくくっていたに過ぎない。
「察し」と、「思いやり」こそが上位と下位者の相互理解であって、上意下達という毅然とした美しい姿が、さも教育であるかの如き風潮は、今もって時代遅れである。だから、自分は高校野球が大嫌いだ。人間が人間を動かすのは難しいが、世にいう無能者といわれる指導者は、石ころを動かすだけでしかない。その程度のことは、どんだけバカな指導者でもやれてしまう。
人間が石ころでなく人間を自負するなら、バカな指導者やバカな親には断固従うべきではなかろう。麻原をバカと見下せず、「反抗できない雰囲気だった」などと、後出しじゃんけん如きの上祐が、新たな宗教を立ち上げて教祖に収まっている。「ああいえばジョーユー」を封印、殊勝な態度で教祖を演じているようだが、宗教家の偽善をあえて問題にする意味はなかろう。